日本ではどちらかというと「母の日」の影に隠れがちな「父の日」。しかし、父の日ができた経緯にはとても素晴らしいエピソードがあり、アメリカでは祝日に制定されるほどの大切な日になっています。この記事では、父の日の起源についてまとめてみました。
父の日の起源と意味
1909年、ワシントン州のソナラ・ドッド(ジョン・ブルース・ドッド夫人)という女性は、「母の日」の説教を聞いていて、「父の日」もあるべきだと考えました。母親の亡き後、ソナラと5人の兄を男手一つで育ててくれた父親を敬愛していたからです。
父親が6月生まれだったため、ソナラは自分が通う教会の牧師に頼み、6月に「父の日」を祝う礼拝をしてもらいました。それは、1909年6月19日で、第3日曜日でした。
これがもとで、ワシントン州では6月の第3日曜日が「父の日」となったのです。
それから、幾人かの大統領によって「父の日」に関する声明などが出されましたが、実際に国民の祝日として定められたのは、1972年のことです。
1861年4月12日、南北戦争が勃発。彼女の父は軍人であり(階級は軍曹)、兵士として召集されました。この戦争は4年間も続き、その間は彼女の母親が1人で家庭を支えなければなりませんでした。ドット婦人を含む6人もの子どもを育てるのは想像以上にハードであり、父親の復員後、母親は過労が元で亡くなってしまいます。
それからは父親1人が子ども達の面倒を見ることになります。戦地から帰ったばかりで、いきなり6人の面倒を見ることとなった父。それはもう、相当の苦労があったと思われます。
しかし、父親は誰とも再婚することなく男手ひとつで子ども達を育て上げました。この立派な父親に感謝した末っ子のドット婦人が、「父親に感謝する日」を作って欲しいと申請。7年という長い月日はかかりましたが、1916年には広く知られるまでになりました。
こんなエピソードを知ると、なかなか母の日の影に隠れがちな父の日も、しっかり大切にしたいと思いました。
日本で父の日が始まったのはいつ?
日本で父の日が広まり始めたのは、
1950(昭和25)年頃からなのですが、認知度は低く
一般的な行事として知れ渡ったのは1980年代になります。デパートなどが、
販売戦略の一つとして父の日をイベント化したことが
一般に広まったきっかけといわれています。
父の日に贈る花
それを見ていきましょう。
父の日の花!
それは、バラの花です。
父の日の提唱者であるソナラが
父の日に父親の墓前に白いバラを供えた。
というところに由来しています。
黄色のバラの花言葉は「嫉妬」や「友情」で、父の日にはふさわしくない言葉のように思えますが、日本では昔から黄色には幸せを象徴する色としてよいイメージがあることから、父の日に黄色いバラを贈るというのが一般的となっています。
日本では日本ファーザーズ・デイ委員会がさまざまなキャンペーンを行っており、父の日には「黄色いリボン」を贈るよう推奨しています。なぜなら、古来イギリスで「黄色」は身を守るための色とされており、この考え方がアメリカに渡り「幸福の黄色いリボン」となり「愛する人の無事を願うもの」となったからです。黄色いリボンは幸せを呼ぶ象徴なんですね。
確かに、黄色いものを見ると、元気が出そうな気がします。
といっても、娘が父に花をプレゼントすることに抵抗ないかもしれませんが、息子が父に花を渡すことに抵抗を感じるかもしれません。大事なのは感謝の気持ちを伝えることですから、そんな時は男同士だったらお酒や財布などの小物など、プレゼントしやすいものを選ぶのもよさそうです。
まとめ
どうしても母の日の印象が強くなりがちですが、父の日も成り立ちを見ると素晴らしいエピソードが背景にあったのですね。
そして、父の日に花をプレゼントするという習慣があったのも知りませんでした。いずれにせよ、母の日も父の日も自分を育ててくれた両親への感謝の気持ちを伝えるとても大切な一日であることには変わりありません。
是非、毎年何か感謝の気持ちを伝えて、家族のきずなを深めていけるとよいですね。











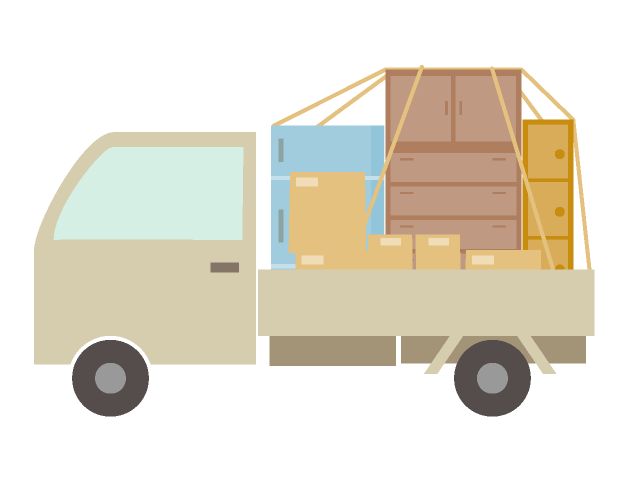
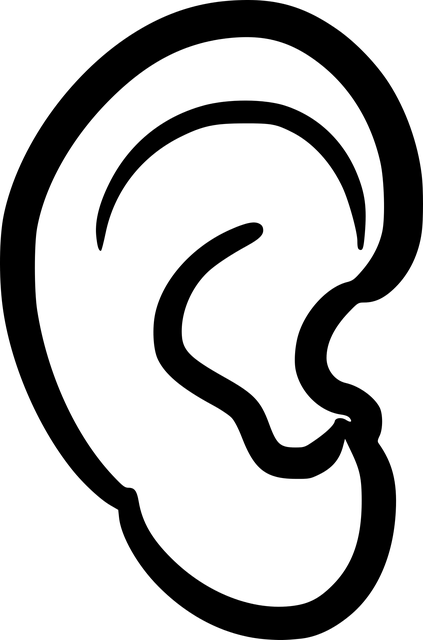
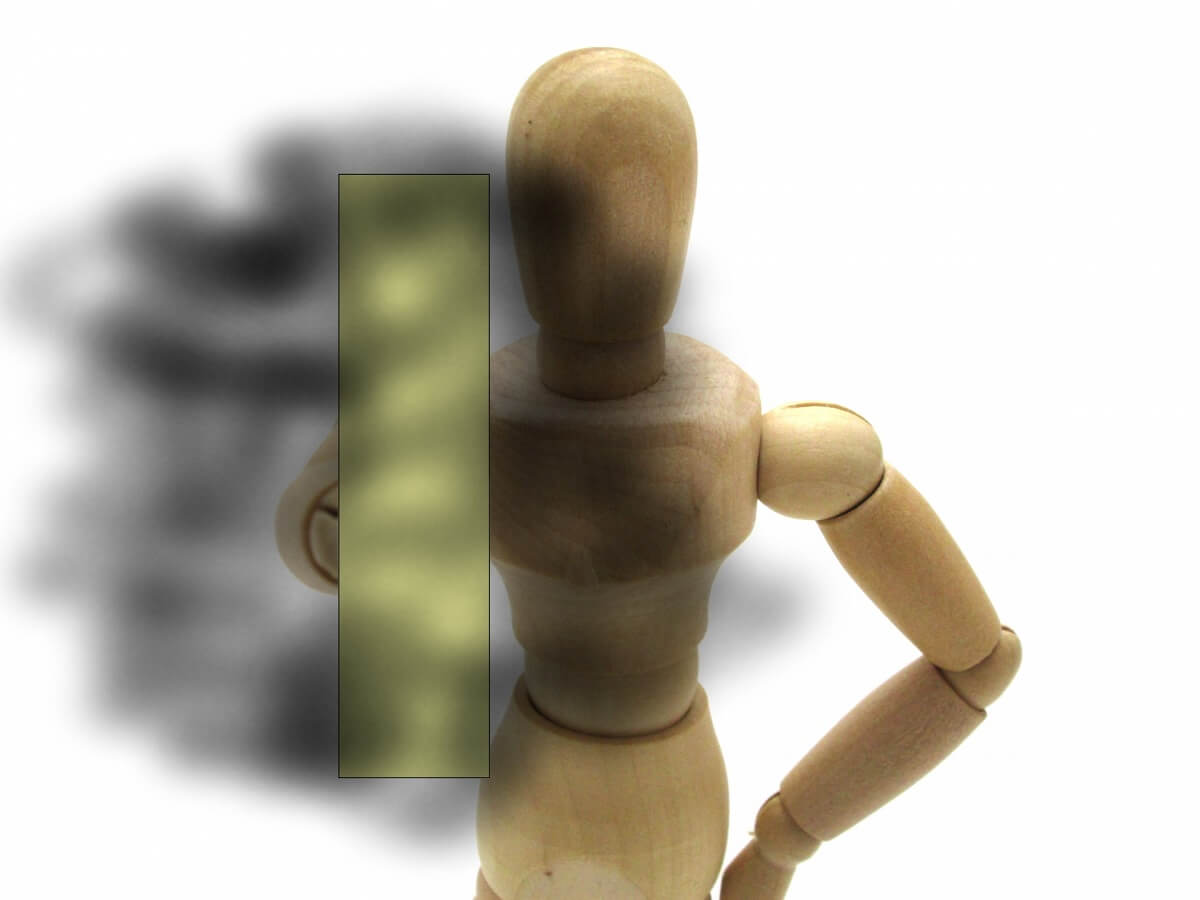







 PAGE TOP
PAGE TOP